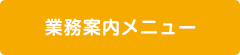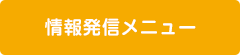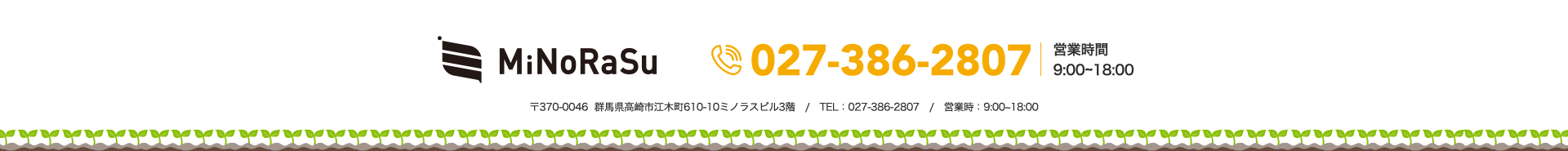2025年(令和6年分)の確定申告では、新たに定額減税が適用されます。
これにより、多くの納税者が所得税と住民税の負担を軽減できる制度ですが、確定申告時に適切な手続きをしないと減税が受けられない可能性もあります。
今回は、定額減税の仕組みや確定申告での記載方法、注意点について解説します。
1. 定額減税とは
定額減税は、2025年(令和6年分)の確定申告で適用される所得税および住民税の減税措置です。
対象者に該当する場合、次の減税が受けられます。
所得税:1人あたり3万円
住民税:1人あたり1万円
例えば、本人・配偶者・子供2人の4人家族の場合、合計で所得税12万円+住民税4万円=16万円の減税が適用されます。
対象者
令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合、年収2,000万円以下)の居住者
同一生計の配偶者や扶養親族(16歳未満の子供も含む)も対象となり、1人あたりの減税額が加算される。
2. 確定申告時の記載方法と注意点
確定申告書第一表の「44番」に記入
・定額減税の対象となる人数と減税額を記入
・例:本人・配偶者・子供2人の4人家族の場合 → 12万円(3万円×4人)を記入
確定申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項」に記入
・対象となる家族の右端「その他」欄に「2」を記入
・16歳未満の扶養親族も対象となるため、忘れずに記入
減税額が所得税額を上回る場合の調整給付金
・確定申告書の44番に記入した減税額が、本来の所得税額を超えた場合、超過分は「調整給付金」として自治体から支給される
・調整給付金は1万円単位で切り上げて支給
・例:減税額が7万円不足する場合、調整給付金は8万円支給
申告しないと減税が受けられない
・確定申告書への記載を忘れると、定額減税が適用されません
・年末調整で定額減税を受けていても、確定申告が必要な場合は再度申告が必須
3. 不足額給付とは
調整給付金を受けた後でも、不足が生じた場合は「不足額給付」として追加支給される可能性があります。
・不足額給付の手続きは、自治体ごとに異なるため、事前に確認が必要
・調整給付金を受けすぎても返金は不要だが、不足がある場合は自治体の指示に従って申請を行う
4. 2025年の確定申告のポイント
・確定申告の期限:2025年(令和7年)3月17日(月)
・e・-Taxで申告すると、マイナンバーカードの読み取りが不要になる場合もあり
・税務署窓口での提出時、収受印は廃止され、代わりにリーフレットが配布
・納付書を使用しない場合、税務署からの納付書事前送付はなし
5. まとめ:定額減税を確実に受けるために
定額減税は、多くの納税者にとって大きな負担軽減となる制度ですが、確定申告時の記載ミスや手続き漏れがあると、適用されないリスクがあります。
・確定申告書第一表の「44番」、第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄の記載を忘れずに
・年末調整済みでも、確定申告が必要な場合は改めて申告が必要
・減税額が所得税額を超えた場合は、自治体から調整給付金が支給される
確定申告をスムーズに進めて、しっかり減税を活用しましょう。