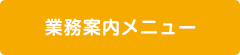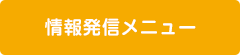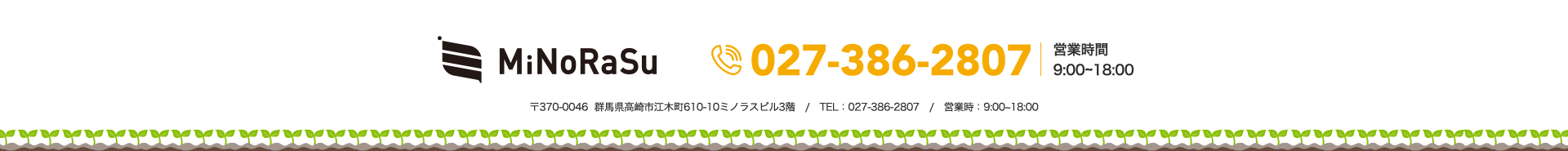どーも、奥野です。
会社を経営していると、時折、「何を犠牲にすれば、理想に近づけるのか」という選択を迫られる場面があります。
そんなとき、私が思い出すのは、深界の闇を背負った研究者――“黎明卿”ボンドルドの存在です。
●理想のために「何かを差し出す」覚悟、ありますか?
ボンドルドの行動原理は、徹底した目的志向。
「私は手段は選びません。なぜなら、目的に意味があるから」
倫理的には完全に“アウト”。
でも彼の信念は、揺るぎなく明確です。
「深界六層の先にある“真理”のためなら、どんな犠牲も厭わない」
私は、経営においてここまで振り切った覚悟を持てるだろうか?と、自問します。
・会社を守るために、誰かの期待を裏切る決断
・利益を守るために、痛みを伴う改革
・未来のために、今を“捨てる”選択
もちろん、ボンドルドのようになれとは言いません。
でも彼の姿勢は、「本当に大事なもののために、覚悟を決められるか」という問いを突きつけてきます。
●“成れ果て社員”を生まないリーダーシップとは
作中で彼は、“カートリッジ”と呼ばれる生きた子どもたちを実験に使い、容赦なく使い潰していきます。
でも彼は、それを笑顔で「素晴らしいですね!」と称える。
ここに、リーダーとしての“最大の落とし穴”があると僕は感じます。
社長として、社員に無意識のうちにこう言っていませんか?
-
「この案件は責任感もってやってね」
-
「君ならできる」
-
「いい感じにやっといて」
それが続くと、社員はいつしか“感情”を失い、“成れ果て”になっていく。
リーダーは、相手の犠牲に鈍感になってはいけない。
ボンドルドのように「善意に見える狂気」を正当化するのは、一歩間違えれば、僕たちの日常でも起こりうるのです。
社員はカードリッジと違って使い捨て出来ませんからね。
●「人を変える」のではなく、「環境を変える」こと
ボンドルドは、人間の能力の限界を知っていました。
だからこそ、外部の環境(ナナチの身体、祈手の量産、呪いの制御)を変えて成果を出そうとした。
これ、経営でも非常に重要な考え方です。
「人が育たない」
「成果が出ない」
「みんな受け身すぎる」
そんなとき、社長や管理者はつい“人を変えよう”としがちです。
でも本当に変えるべきなのは、
制度であり、評価軸であり、心理的安全性のある職場環境だったりします。
ボンドルドは極端すぎたけれど、彼の“外部からのアプローチ”という視点には、大きなヒントがあります。
●「覚悟」と「狂気」の境界線に立つ社長へ
経営は常に、“正しさ”と“現実”の間に立たされます。
・理想を追いすぎて孤立するか
・現実に流されて信念を失うか
・その中で、自分の芯をどう保つか
ボンドルドのように、何かを犠牲にしてでも進むことが、時に必要かもしれません。
でもそのとき、「誰のためにそれをやるのか」を見失ってはいけない。
「素晴らしいですね!」と笑うその前に、
誰が傷ついているかを、社長はちゃんと見なければいけない。
●あなたにとって、“黎明卿”のような覚悟とは?
ボンドルドは間違いなく“悪役”です。
でも、そこに学びがないわけじゃない。
・理想への執着
・手段を選ばぬ信念
・多くを抱えてでも前に進む姿勢
社長は、彼の“狂気”を、覚悟のヒントとして受け取ることができる。
あなたが信じている“理想”は何ですか?
そしてそれを貫くために、どんな“覚悟”を持っていますか?